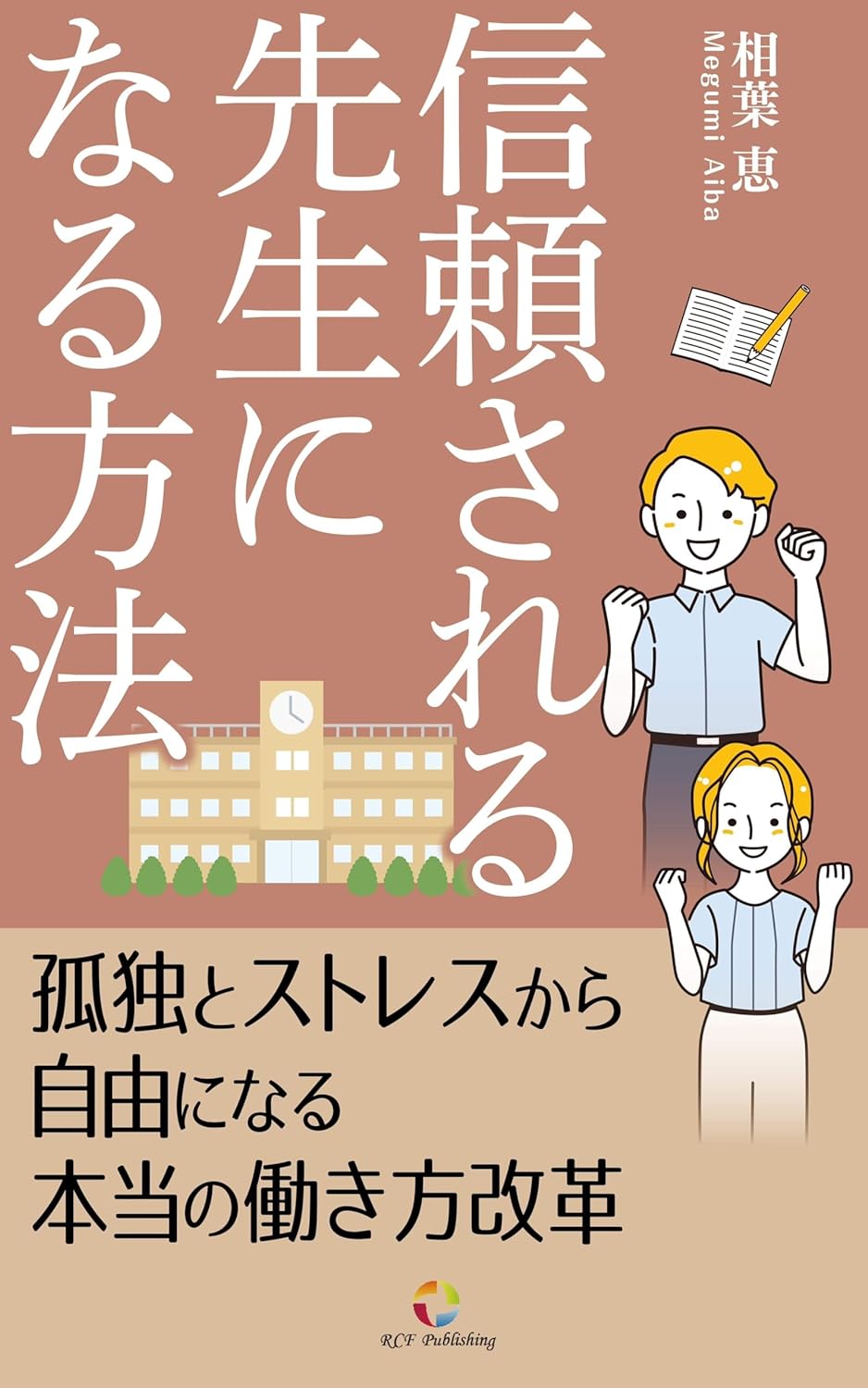ブログ
あなたの「信頼」の定義を教えてください。
「信頼」とはあなたにとって、どういうものですか? 面白いことに、この質問をすると、 一人ひとり全く違う返答が返ってきます。 信頼についての「定義」を教えてほしいのです。 あなたにとって、「信頼」とは何ですか? 「信頼」についてどう思っているのかを教えてください。 私にとって「信頼」とは お互いがありのままでいられる状態。 その場にいることでその力を発揮 ...続きを見る
信頼されるから。絶対、大丈夫!
声を大にして言いたい。 あなたは絶対に大丈夫。 だから不安に飲まれないでほしい。 未来に失望しないでほしい。 「私に信頼が築けるわけがない」なんて、落ち込まないでほしい。 今のあなたがどんな状況でも、 どんなに苦しくても、 うまくいかないことばかりでも、 絶対大丈夫。 いきなり、何だと思われたかと思います。 このタイミングでお伝えしたいと思ってブログを ...続きを見る
自分の人生を生きると、信頼されるようになる
自分の人生を生きていますか? この問いに、あなたはどう答えますか? 「ものすごく楽しんで生きているよ!」という方もいれば、 「当たり前でしょ?」という方もいれば、 「それすら、よく分からない。生きていると思うけど…」という方もいるかと思います。 実際に私は「当たり前でしょ?」と言いつつ、「でも実際はどうなんだろう?」という状態がずっと続いていました。 ...続きを見る
1日5分。その継続が信頼となる。
1日5分。自分のために時間を取れるかどうか…がカギ。 なぜ自分のために時間をとる必要があるの? そんなことして何になるの? まさにタイトルを見て思った人であれば、その人にとって1日5分だけでも自分の時間をとることで、人生が大きく変化します。 本当は30分、もっと言えば1時間取れたらなお良いと思います。 でも実際、忙しい教員の方にとってはそれは厳しい ...続きを見る
信頼される先生になる方法~孤独とストレスから自由になる本当の働き方改革~
信頼される先生になる方法 ~孤独とストレスから自由になる本当の働き方改革~ この度、電子書籍を出版することになりました。 ↓ 信頼される先生になる方法 何度かにわたり、信頼についてこのブログでお伝えさせていただいております。 私自身、信頼される先生になりたい!と望んでいても、現実的にはとても難しく、日々の忙しさの中でただただ「こなす」という悶々とし ...続きを見る
自分と繋がれば、自然と信頼される人になる
自分と繋がることは信頼の土台。 以前、自分と繋がることについて、同じような記事を書かせていただきました。 ↓ 信頼は…自分を知ることが大事 今回は、さらに深掘りしていこうかと思います。 実は、自分と繋がるだけで、それが土台としてしっかりできていれば、誰でも何があっても生きていけるのです。 つまり、その土台を教員が持っていれば、教員が自分とさえ ...続きを見る
中西茂理事(元読売新聞編集委員)が連載を始めました。タイトルは「共育の杜を歩く」。全国の「杜」を訪ね歩きます。
「共育の杜」のウェブページで中西茂理事(元読売新聞編集委員)が連載を始めました。 タイトルは「共育の杜を歩く」。全国の「杜」を訪ね歩きます。 ○「共育の杜を歩く」(概要はこちら) ...続きを見る
信頼を築きたいのなら、働き方を見直すべき⁉
働き方改革と、信頼のこと。 今回のタイトルをみて、疑問に思った方や否定したくなる方がいたのではないかと思います。 働き方と信頼に関係なんてないのではないか…? もちろん、直接的に関係はないように思われるでしょう。 でも、私は思うのです。 働き方を少し変えるだけで、信頼されるようになるのではないか? そのような問いを、学校で働いていた時に思ったこ ...続きを見る
あなた自身の「声」を聞けば、自然と信頼が築ける?
あなたの「声」を無視していないですか…? 率直に聞きたいのです。 子ども達の前に立つ立場であるあなたに対して、 「あなたはちゃんと自分の声を聞いてあげていますか?」 と問いたいのです。 どういうこと?と思った方も多いかと思います。 自分の声は普段から聞いてる、という答えががえってきそうです。 でも、、、 本当に聞こうとして耳を傾けているでしょうか&h ...続きを見る
【緊急開催】 精神疾患で倒れる教員過去最高に! ~この危機の克服のカギはココにある~
文科省は、2022年度(令和4年度)教員の精神疾患による病気休職者数は6,539(全教員数の0.71%)で、2021年度(5,897人)から642人増加し、過去最多となったことを公表しました。 しかし、この数字は学校現場の危機的状態を示しているとは言えません。病気休職を取得することなく復帰した教員、つまり病気休暇をとった教員もいるからです。1ヶ月以上の病気休暇取得者、及び病気休職者 ...続きを見る