発達検査のメリットデメリット
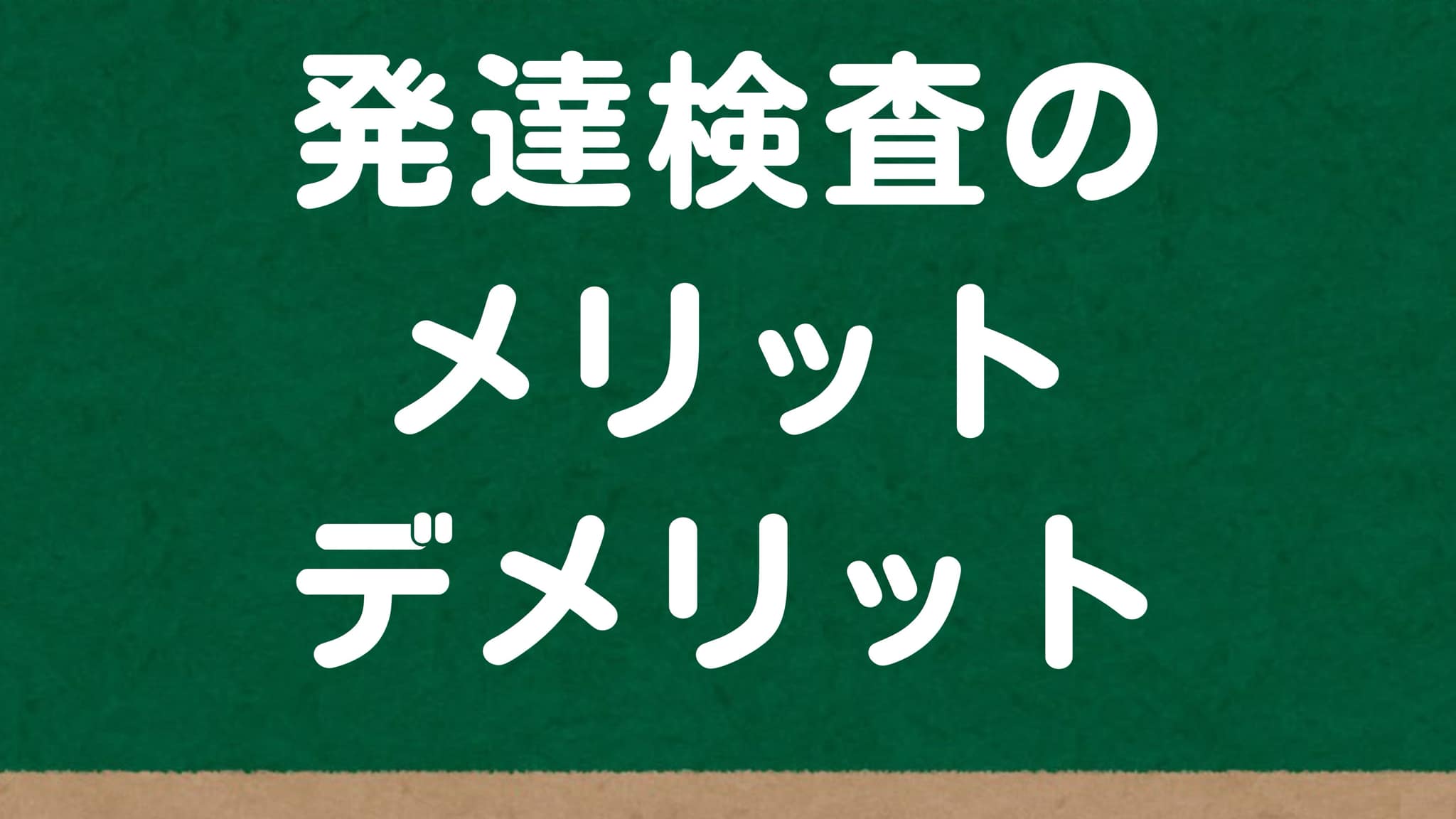
はじめまして。叶めぐみと申します。
発達障害の子供たちを育てた経験をもとに
こちらのブログを書かせて頂くことになりました。
35人の学級なら3人はいると言われている発達障害の子供たち。
支援級の先生はもちろん、通常級の先生方にとっても気になる存在だと思います。
その子供たちの背景や保護者から見えるものなど、
実体験をもとに当時を振り返りながら書かせていただきます。
発達障害について、少しでも理解が広がるきっかけになると幸いです。
これからどうぞよろしくお願いいたします。
それでは、第1回目としては、発達検査と発達障害の診断について書いてみます。
「この子、ほかの子と違うんだよなぁ、
発達検査を受けた方がいいんじゃないかなぁ」と思われるお子さんが身近にいらっしゃる方に読んで頂けると幸いです。
しかしながら、保護者としては学校や保育園から 「発達検査を受けて来て下さい」と言われると、結構構えてしまう方がいらっしゃるのも事実です。
そこで、この記事では、
・1.発達検査により発達障害の診断を受けてよかったこと
・2.よくなかったこと
・3.先生から伝えられるときにこんな配慮があるとありがたい
ということを書いてみます。
1.発達検査により発達障害の診断を受けてよかったこと
(1)親として我が子に合った関わり方を知ることができたこと
もし、何も知らないままだったら・・・
「なんでできないの!!」という気持ちから、子どもができないことを無理やりやらせようとして親子関係か悪くなっていたかもしれません。そうならなかったのは、発達障害の診断があったからです。
(2)人間としての器・枠を広げられた経験
自分の常識が通らない事だらけの発達障害を持つ子の子育てでは育てる側の人間の器・枠を広げる事が 必須となります。
私はフルタイム正社員で仕事も忙しかったため、発達障害という診断がなければ、そこまで覚悟をもって子育てに真剣に取り組めなかったかもしれません。
(3)相手への伝わりやすさの配慮
発達検査を受け、発達障害と診断され、現実を受け入れざるを得なくなります。しかし、普通の子育てと同じく、将来、子ども達が自立・自律できる大人になるために必要なことを伝わりやすく伝え教える必要がありました。
しかし、「普通に伝える」では伝わらないのです。それでもなんとかしなければという気持ちが沸き起こったからこそ、いろいろな知識や学びを得て伝わりやすい方法を知る事ができ、その方法を実行できたのだ思っています。
2.発達検査を受けてよくなかったこと
(1)親同士の繋がりが作りづらい
発達障害の子を持つ親の悩みとして、
・子どもがなかなか成長してくれない
・子ども同士での関わりを持ってくれない、うまく遊べない
というのがあります。
ちなみに、発達障害の子を持つ親は、普通の発達のお子さんのことを「定型発達」と呼びます。
その定型発達のお子さんの話を聞くと、どうしても自分の子と比べ落ち込んでしまうという事が度々ありました。
また子どもは子ども同士の友達を作って来ませんので子どもを通じてのママ友というのが、なかなかできませんでした。
(2)発達障害の診断をされても 根本へのアプローチ方法は示されないケースが多い
医療機関にかかると投薬を薦められることが多いです。投薬は、対処療法であり根本の部分の改善ではありません。
根本へのアプローチ方法として、幼児の間は 発達障害の診断が下りると公的な機関での作業療法や言語訓練などを受けることができます。しかし、小学校に上がると療育を受けられる機会が激減してしまい、障害への根本的なアプローチが受けられない状況に陥りがちです。
その結果、 親として途方に暮れ、諦めて過ごすという方が非常に多いように思います。
3.先生から伝えられるときにこんな配慮があるとありがたい
発達検査を受けるとなったとき、保護者は我が子が発達障害の診断が出てしまったらどうしようという不安を持ちます。見通しが持てないからです。また育てるために覚悟も必要となるからです。
見通しを持てるようになることも、覚悟を持てるようになることも人によって時間はかかります。
反対に、見通しが持てるようになると希望を持て、覚悟もできてくる場合もあります。
そんな揺れ動く気持ちに寄り添って頂けるとありがたいです。
また、不安のある方や迷っている方へ「こんなお母さんもいるんだって」と私と繋いで頂けることで、その親子にとって前を向けるきっかけになるかもしれません。
全体として
発達検査や発達障害と診断された際のメリット、デメリットを書いてみました。
決して、障害者というレッテル貼りが目的ではありません。
発達検査から特性を知り、その子の可能性を広げるものであってほしいと望みます。また支援方法を知ることはとても重要な事です。
とはいえ、根本へのアプローチが提示される事が少ないという問題があるのも現状です。
なお、根本へのアプローチ方法は存在します。
その辺を親として追求し続けた結果を貢献できる形にできればと思い、電子書籍や講座としてまとめて必要な方へお伝えしている活動をしています。
最後に電子書籍や動画講座などの概要も載せておきますので、のぞいて見て頂けると幸いです。
叶めぐみ プロフィール
会社員をしながら、双子の発達障害の男の子を育てた母親。現在、子ども達は成人し就労している。
子ども達が小学校の間は、登校の付き添い、朝の会までの補助、遠足や宿泊学習の付き添いを続けつつ、先生方と良好な関係性を築いて来た。
子育てや人間関係の困難な場面を乗り越えるべく、発達支援やコーチング、カウンセリングなどのスキル獲得や自己成長の場に身を置き続ける中で、2016年に佐々木浩一氏の提供するプログラムに出会い、その後も学びと実践を継続中。
現在では同じ発達障害の子を持つお母さんを含む女性たちを中心に各種講座やメンタルサポート(トラウマの解放を含むカウンセリング、コーチング)を行っている。
子育てや自身のメンタル立て直しを通じて経験した「相手を尊重し、寄り添い、受け入れ、励まし、共に歩む」というスタイルをクライアントに実践し、好評を得ている。
また人生の目標として「自分の過去の経験を人に貢献できる形にする」という志を持ち、現在までに電子書籍を3冊出版。
現在、商業出版の企画案が通り、「心が弱った状態から抜け出るための習慣(仮)」を執筆中。
発達障害の根本原因に対するアプローチについてまとめた電子書籍や動画講座を配信中
発達が気になるお子さんと関わっておられる方にご紹介頂けますと幸いです。
自然体でうまくいく発達凸凹育児
★kindle unlimitedで無料でお読みいただけます
この電子書籍をもとにした動画講座


