身体が過緊張になってませんか?
【更新日】
2025年4月5日(土)
コミュニケション・外国語運用能

身体が「過緊張」になってませんか?〜まずは自分の身体を緩めて信頼していこう〜
4月になって新しい出会いに
期待と不安があるのは子どもたちだけではないですよね。
きっと教員の方も、
ドキドキとワクワクと、責任感と期待と…様々な想いが交錯しているかと思います。
そんな今だからこそ、
ご自身の「身体」に意識を向けてみてください。
あ、肩に力が入ってるな。
頑張りすぎてるのか、腰が痛い。
など、特にこの時期は子ども達に全集中している方も多いので
ご自身の身体に目を向けることなんて
全くしてないのではないでしょうか?
さらに職場が変わった方なら
なおさら力が入ってしまっていることでしょう。
そこをあえて、
気づいた時に身体に意識を向けてください。
子どもたちが帰った後、
子どもたちが登校する前、
それだけでもいいと思います。
身体が「過緊張」な状態だと、何が起こると思いますか?
緩んでいる方が、
リラックスしている方が、
仕事としての効率や子どもたちと関わる上で
良いのはお分かりだと思います。
他人、つまり子どもたちや同僚からしたら、
緊張状態の人と向かい合うとそれだけで疲れてしまいますよね。
ギュッ!と緊張状態なので、
それが相手に伝わってしまいます。
すると、相手にもその身体の感覚が伝わってしまい、望むような信頼関係は難しくなるのは
いうまでもありません。
そんな私は、
今思うと、常に学校にいた時は「過緊張」状態だったといっても過言ではありませんでした。
唯一、子どもと休み時間に遊んでいた時は
身体が緩んでいました。
だからそんな風に無邪気に遊ぶようになってからは、
教室や学校での仕事がどんどんスムーズに楽しくなっていったのだと思います。
では「過緊張」だと、他にどんな弊害があると思いますか?
ひとつに、身体が「過緊張」だと、それに反発するかのように
人間関係がうまくいかなくなります。
これは先ほど述べたように、相手にとって
「自分は受け入れられていない」と無意識に感じてしまうのです。
それをいくら頭の中で「私は信頼している」「あなたを大切に思ってる」とした所で
身体が反発状態であれば、相手には伝えたくても伝わらないのです。
アファメーション、といったものも大事ですが、それ以上に身体を過緊張状態から緩めてあげることの方が
よっぽど早く、よっぽど伝えたいことも伝わっていくというのが、私の体験上感じることです。
さらに、身体が過緊張だと、外から何かを得ようと必死になります。
どういうことかというと、身体がギュッとなっているので、それを緩めたい、楽になりたいと身体が思うのです。
だから無性に食べたくなったり、買い物で爆買いをしてしまったり、誰かからの承認が欲しくなったり…といったことが起こります。
自分の身体が飢餓状態になるので、外に外に…と楽になれるもの、リラックスできるものを求めていくのです。
その状態で、子ども達の前に立つと考えると、
どうでしょうか?
とてもじゃないけど、
無理やりなら可能だけど、
子どもたちと信頼を築ける状態かというと
とても難しいのではないかと思います。
ではどうしたら身体の「過緊張」が取れていくのでしょうか?
つまりはリラックスすれば良いんです。
そんなことは分かってると思います。
力を抜いて〜ため息ついて〜肩の力を一回入れて〜脱力〜
といった感じで緩むならそれで良いんですが、
私はそんなことをしても
気持ち的に「変わった…かも?」ぐらいで
結局は「過緊張」で1日過ごしていました。
ではどうすればいいのか?それを具体的にやっていくこととして、
まずは「ため息」からみていきたいと思います。
まずため息をしてみてください。
「は〜」と息を出した時に
胸で止めていませんか?
それだと余計に疲れるんです。
そうではなく、その息を肚、つまりおへその下あたりまで「ぐー」っと落としてあげるんです。
自分の身体の喉から肺から胃を通って下まで生きを落としてあげる。
それだけでも、緊張のとれ具合が違ってきます。
吐き切る、といった感じです。
そんなことが意味あるの?
という方はとりあえずやってみてください。
私は過緊張すぎて、初めはそれすら分からなかったです。
感覚が鈍りすぎていたんですよね笑
そしてもうひとつ。
人はみな、身体の奥をみていくと、皮膚があり、そのもっと深いところには細胞があり、人として形成されています。
その細胞が緩むように意識してみるんです。
難しいと思います笑
私もそれを聞いた時、「細胞?!」と驚くと同時に「そんなことできない!」と出てきて、やらずにいました。
でもふとした時に細胞というものに意識を向けて、緩んでみようとやってみたら
本当に力が抜けた感覚があって驚いたのを覚えています。
だから騙されたと思って、ちょっとでも続けてみてください。
現代人は本当に「過緊張」の塊だと思います。
それは特に日本人を見ていて思います。
色々なところに気がつくが故に、
そしてその根本に持っている調和という性格故に、
ご自身の身体を緊張状態にさせることによって
自らを守ってきたともいえます。
でももっともっと力を抜いて良いんです。
頑張らなきゃ!
それはとても大切なことです。
でも、力を入れても抜いても、
結果は変わらないとしたら?
むしろ力を抜いた方が
もっと本来の力を発揮できるとしたら?
行くぞー!という気合いは必要です。
でも身体から緩んだ上で、必要なところに力を入れていくとその気合ももっともっと士気の高い、みんなを巻き込んでいけるものとなるんです。
たかが、身体。
されど、身体。
私たちは身体なくしては存在できません。
そして細胞なくしては存在していません。
力を抜く。
でも肚は抜かない。
昔の日本人が凄かったのは
この身体の使い方が出来ていたから。
私たちはそれを思い出せば
本来の力が戻ってくるんです。
呼吸をする時に、ため息をつく時に、
まずは肚、ヘソの下まで落としてあげる。
そして細胞を緩めるように意識してみる。
できる、出来ないなんて、どっちでもいいんです。
まずは意識をしてみるところから。
信頼を築く大前提である、ご自身の身体に
少し、目を向けてあげてください。
---------------------------
共育の杜のセミナー情報はこちらから
↓
セミナー情報
_________
この度、電子書籍を出版することになりました。
良かったら読んでみてください。
↓
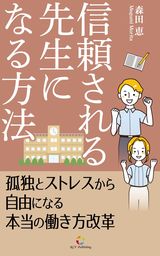
―――――――――
定期的に共育の杜からメルマガを配信しています。
↓
メルマガ登録はこちら
―――――――――
ブログに関しての質問や感想、聞きたいこと、トピックとして挙げてほしいことなどありましたら、下記までメッセージをください。
↓
こちらから
■ 執筆者情報■森田恵
子どもが好きで教員を目指すが、挫折。退職を考えるも奮闘し、次第に毎日が楽しく、子ども達からも「先生大好き!」と言われるように。そんな教員時代の経験をもとに、悩みを持つ人に役立つことを伝える活動を行っている。結婚を機に、渡米。10年の小学校教師の経験を活かし、渡米後は日本語の家庭教師や、現地校にて日本の文化を伝え、日本語を教えて過ごす。現在3児のママ。2度の流産経験により、食や環境、ママの状態が子どもへ与える影響などに興味を持つ。さらに、意識によってもたらされる変化を日々、体感を通して実践している。


