焦りを静めるたったひとつの方法〜それは、「息を思い出す」こと。
【更新日】
2025年11月1日(土)
コミュニケション・外国語運用能

はじめに
11月。学期も後半に入り、
学校全体が少しずつ慌ただしさを帯びてきます。
子どもたちは学習や行事の疲れが溜まり、
集中力が途切れやすくなる時期です。
教師も評価やまとめ、
行事準備に追われ、
気づけば息を詰めて仕事をしている。
そんなことはないでしょうか?
そんな中で、教室の空気が落ち着かないとき。
実は、教師の焦りや不安が、
無意識に子どもへ伝わっていることがよくあります。
教師の「焦り」が教室をざわつかせる
たとえば、こんな思いを抱えていませんか?
「またトラブルが起きたらどうしよう」
「あの子たち、またケンカしそうだな」
「ちゃんとまとめなきゃ、時間がない」
この「どうしよう」のエネルギーは、
まるで目に見えない波のように教室全体に広がります。
子どもは大人の表情や呼吸の浅さを
驚くほど敏感に感じ取ります。
つまり、教師が焦ると、
子どもも落ち着かなくなる。
だからこそ、「子どもを落ち着かせる前に、
自分が落ち着く」ことが何よりも大切です。
どうなったらいいのかを、自分に問う
トラブルを恐れる前に、こんなふうに自分に問いかけてみてください。
「トラブルが起きても、それを通して子どもたちが学び合えるならいい」
「ケンカしても、そこから関係が深まればそれでいい」
「みんなで穏やかに過ごせたら、それが一番うれしい」
焦りや不安を「ダメなこと」として押し込めず、
「自分はどうありたいか」
「どうなったら安心できるか」を
一度立ち止まって見つめる。
その瞬間、呼吸は自然に深くなり、
心も少し柔らかくなります。
呼吸を「下に落とす」
焦っているときの呼吸は、
胸や喉のあたりで止まっています。
頭ばかりが働き、思考がぐるぐる回る状態。
そんなときは意識的に、呼吸を下腹(丹田)に落とすイメージで。
⭐️吸うときは「空気が骨盤まで届く」ように
⭐️吐くときは「地面に根を下ろす」ように
この呼吸を続けていると、
頭の中の「どうしよう」という声が少しずつ遠のき、
心が“今ここ”に戻ってきます。
教師が地に足をつけて立つことで、
教室全体が落ち着く。
それを子どもたちは肌で感じ取ります。
呼吸を「自分の味方」にする
もし「呼吸なんかで変わるわけがない」と思うなら、
どうか一度だけ、焦った瞬間に試してみてください。
たかが呼吸。
されど呼吸。
私自身、焦りや不安、パニックに呑まれそうな場面で、
この呼吸に何度も助けられてきました。
子どもが荒れて収拾がつかないとき。
理不尽な要求を受けて、涙が出そうになったとき。
「もう無理かもしれない」と思ったとき。
そんな時ほど、呼吸に依存して、呼吸に頼っていい。
息を吐くたびに、「私は大丈夫」「今ここにいる」と心に戻ってくる。
それが“自分軸”を取り戻すということです。
呼吸が教室を変える
あなたが呼吸を整えるだけで、
声のトーンが変わり、
言葉が変わり、
子どもの反応も変わります。
教師の呼吸は、教室のリズムそのもの。
深呼吸するたびに、
空気が少しやわらぎ、
子どもの表情も変わっていく。
その変化を一度でも感じたら、
呼吸の力をきっと信じられるはずです。
おわりに
焦りも不安もあっていい。
ただ、そのたびに「呼吸へ戻る」ことを
思い出してください。
呼吸は、教師にとって最も身近で、
最も確かなセルフケアです。
子どもの荒れにも、同僚の圧にも、そして自分自身の心の波にも。
呼吸は、あなたを静かに支え続けてくれます。
--------------------
共育の杜のセミナー情報はこちらから
↓
セミナー情報
_________
この度、電子書籍を出版することになりました。
良かったら読んでみてください。
↓
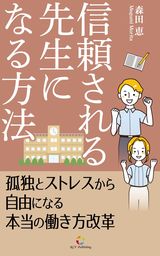
―――――――――
定期的に共育の杜からメルマガを配信しています。
↓
メルマガ登録はこちら
―――――――――
ブログに関しての質問や感想、聞きたいこと、トピックとして挙げてほしいことなどありましたら、下記までメッセージをください。
↓
こちらから
■ 執筆者情報■森田恵
子どもが好きで教員を目指すが、挫折。退職を考えるも奮闘し、次第に毎日が楽しく、子ども達からも「先生大好き!」と言われるように。そんな教員時代の経験をもとに、悩みを持つ人に役立つことを伝える活動を行っている。結婚を機に、渡米。10年の小学校教師の経験を活かし、渡米後は日本語の家庭教師や、現地校にて日本の文化を伝え、日本語を教えて過ごす。現在3児のママ。2度の流産経験により、食や環境、ママの状態が子どもへ与える影響などに興味を持つ。さらに、意識によってもたらされる変化を日々、体感を通して実践している。


