授業が「呼吸」する〜焦らない先生がつくる、子どもの集中が深まる45分
【更新日】
2025年11月9日(日)
コミュニケション・外国語運用能

学期の後半に入り、
授業のペースも少しずつ速くなっていく時期です。
「進度が遅れている」
「この単元を今週中に終わらせなきゃ」
そんな焦りが、教室全体の空気を
知らず知らずのうちにピリッとさせているかもしれません。
でも、子どもたちは教師の
『呼吸』を感じ取っています。
先生の呼吸が浅く、早くなっていると、
子どもたちの呼吸も自然と同じリズムになります。
逆に、先生の呼吸がゆっくり深く落ち着いていれば、子どもたちの集中も自然と深まっていく。
授業の空気を整える第一歩は、「先生自身の呼吸」にあるのです。
■ 呼吸で変わる「言葉の力」
先生の仕事は、1日中「言葉」を使うこと。
しかも、ただ話すだけではなく、「言葉を教える」立場でもあります。
だからこそ、忙しい中でつい、言葉を「道具」のように扱ってしまう瞬間があるかもしれません。
でも、言葉の前に「一呼吸」置くだけで、伝わり方が驚くほど変わります。
たとえば、
朝のあいさつの前に、ひとつ深呼吸。
その息を感じながら「おはようございます」と言う。
たったそれだけで、教室の空気がふっと落ち着きます。
声が通る、というより「届く」ようになる。
子どもたちは無意識にそれを感じ取り、
「なんか今日の先生、落ち着いてる」と思う。
すると、不思議とざわめきもおさまっていくんです。
■ 言葉は「息+音」
実は、言葉は「息」と「音」でできています。
どんなに丁寧な言葉を選んでも、
呼吸が浅いと、声が上ずったり、響きが軽くなります。
逆に、お腹から息を流して声を出すと、
自然と落ち着いたトーンになります。
子どもたちは内容よりも、その「響き」を敏感に感じ取ります。
だから、注意をするときほど、
呼吸を意識することが大切です。
たとえば、
「静かにしなさい!」を息を止めて言うと、
圧が強く伝わります。
でも、一呼吸おいて、息を吐きながら「静かにしようか」と言うと、声に“余白”が生まれ、
子どもの心に届きやすくなります。
ほんの数秒の呼吸の差。
でも、それが「対立」ではなく「共鳴」に変わる瞬間です。
■ 教室の空気は、先生の呼吸で変わる
ある先生がこう話してくれました。
授業が始まる前、深呼吸して
「よし、今日もこの子たちと学ぼう
ってつぶやくだけで、
子どもの反応が違うんですよ」
不思議なようで、実はとても理にかなっています。
教師の身体が落ち着いていると、声に安定感が出て、子どもはその“安定”を無意識に感じ取ります。
それはまるで、海の波が穏やかになっていくようなもの。
教師が整うことで、教室が整う。
呼吸は、その最もシンプルで確実な方法です。
■ 「授業を整える」ための3つの呼吸習慣
すぐに取り入れられる簡単な方法を3つ紹介します。
1. 授業の始まりに、深呼吸をひとつ
立ち上がる前、または「起立!」の前に一息。
空気が落ち着いてから第一声を出すと、
教室の空気が変わります。
2. 話の切り替えごとに、息を吐く
「さて、次は〜」の前に一呼吸おく。
話すテンポが自然に整い、聞き手も「ついていきやすく」なります。
3. 終わりのあいさつを、息の流れに乗せて
最後のあいさつも、深呼吸の延長で。
言葉が柔らかく、余韻が残ります。
どれも特別なトレーニングではありません。
「今日の授業、息が浅かったな」と感じたら、
それに気づけるだけで十分。
呼吸に気づくこと自体が、
もう『リセット』なんです。
最後に
授業づくりは、言葉づくり。
そして、言葉は呼吸から生まれます。
焦りや緊張で呼吸が上がると、声も、空気も、どこかとがっていきます。
でも、ひとつ息を吐くだけで、空気がやわらかくなり、子どもとの関係も少しずつ変わっていく。
たった一言の前の一呼吸。
それが、クラス全体をやさしく整える力を持っています。
--------------------
共育の杜のセミナー情報はこちらから
↓
セミナー情報
_________
この度、電子書籍を出版することになりました。
良かったら読んでみてください。
↓
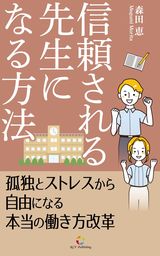
―――――――――
定期的に共育の杜からメルマガを配信しています。
↓
メルマガ登録はこちら
―――――――――
ブログに関しての質問や感想、聞きたいこと、トピックとして挙げてほしいことなどありましたら、下記までメッセージをください。
↓
こちらから
■ 執筆者情報■森田恵
子どもが好きで教員を目指すが、挫折。退職を考えるも奮闘し、次第に毎日が楽しく、子ども達からも「先生大好き!」と言われるように。そんな教員時代の経験をもとに、悩みを持つ人に役立つことを伝える活動を行っている。結婚を機に、渡米。10年の小学校教師の経験を活かし、渡米後は日本語の家庭教師や、現地校にて日本の文化を伝え、日本語を教えて過ごす。現在3児のママ。2度の流産経験により、食や環境、ママの状態が子どもへ与える影響などに興味を持つ。さらに、意識によってもたらされる変化を日々、体感を通して実践している。


