「ちゃんとしなきゃ」を手放した日から、子どもとの時間が変わった
【更新日】
2025年7月9日(水)
コミュニケション・外国語運用能

「ちゃんとしなきゃ」を手放した日から、子どもとの時間が変わった
「ちゃんと指導しなきゃ」
「ちゃんと見ておかなきゃ」
「ちゃんと書類も、行事も、保護者対応も…」
そんなふうに、過去の私は“ちゃんと”を重ねながら毎日を過ごしていました。
一つひとつは当たり前のことだと思っていたけど、
ふと気づくと、どこか息苦しい。
職員室では笑っていても、
家に帰ると何もしたくなくて、
ごはんを食べる元気さえ湧かない。
そんな日々を繰り返していました。
そんなある日のこと。
ある児童Aくんが友達と喧嘩になり、
話の仲介をして、クラスみんなで話し合って。
そんな日が終わり、子供たちを返した後に教室に戻ってみると、教卓の上にメモが一枚。
「せんせい、きょうもいっぱいありがとう。Aより」
たった一言。でもそのとき、胸にストンと落ちるものがありました。
その日、その話し合いは私的には
“ちゃんと”やれてない出来事でした。
さらに、その話し合いで
やらねばならないことも出来ず、計画もズレて、授業もバタバタ。
教員として失格だ…と落ち込んでいた放課後。
それなのに、この子は私のことを“ありがとう”って思ってくれてた。
「ちゃんとやれてるかどうか」は、きっと私だけが気にしていたのかもしれない。
それよりも、“どんな気持ちでそこにいるか”のほうが、ずっと子どもに伝わるんだ!
そんなふうに思えた瞬間でした。
それ以来、私はちょっとだけ「ちゃんと」をやめてみることにしました。
完璧じゃない授業でもいい。
連絡帳のコメントが一言だけでもいい。
書かない日があってもいい。
無理に全部を抱え込まなくてもいい。
抜けててもいい。
そう思えるようになると、不思議と子どもとの時間が、ふわっと軽くなっていきました。
「先生、今日なんか楽しそうだね!」って言われるようにもなりました。
それはきっと、自分自身が“がんばりすぎる自分”から
少し自由になれたからだと思います。
「ちゃんとしなきゃ」って、
実は“自分を守るため”の言葉でもあると思うんです。
そうしないと怒られるかも。
周りから評価されないかも。
子どもに迷惑をかけるかも。
いろんな「かも」の不安から、自分を守るための『頑張り』だったんだと思います。
でも、本当に大事なのは「完璧な指導」じゃなくて、子どもたちに必要なのは
安心してそこにいられる大人の存在。
ちょっと失敗しても、バタバタしても、
どこかでホッと笑っていられる教員。
そんな大人のそばにいることで、
子どもも自然と安心して、
自分らしくいられるようになる。
私はそう思います。
あなたは今、どんな「ちゃんと」に縛られていますか?
もちろん、教員として責任感を持つことはとても大切です。
でも、その中に少しだけ余白を持たせてみてください。
「今日はこれだけでいいや」って、自分に小さなOKを出してみてください。
意図が変わると、空気が変わります。
空気が変わると、子どもの表情が変わります。
それが積み重なって、教室が少しずつ変わっていきます。
「ちゃんとしてない自分でも、大丈夫だった」
そう思えたあの日から、
私の教員生活は少しずつ、でも確かに変わり始めました。
あなたの“ちゃんと”は、誰のためのものですか?
良かったら、その問いをご自身にしてみてください。
意外な答えが返ってくるかもしれません。
-------------------------
共育の杜のセミナー情報はこちらから
↓
セミナー情報
_________
この度、電子書籍を出版することになりました。
良かったら読んでみてください。
↓
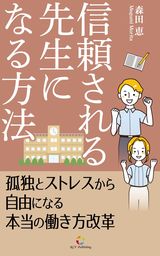
―――――――――
定期的に共育の杜からメルマガを配信しています。
↓
メルマガ登録はこちら
―――――――――
ブログに関しての質問や感想、聞きたいこと、トピックとして挙げてほしいことなどありましたら、下記までメッセージをください。
↓
こちらから
■ 執筆者情報■森田恵
子どもが好きで教員を目指すが、挫折。退職を考えるも奮闘し、次第に毎日が楽しく、子ども達からも「先生大好き!」と言われるように。そんな教員時代の経験をもとに、悩みを持つ人に役立つことを伝える活動を行っている。結婚を機に、渡米。10年の小学校教師の経験を活かし、渡米後は日本語の家庭教師や、現地校にて日本の文化を伝え、日本語を教えて過ごす。現在3児のママ。2度の流産経験により、食や環境、ママの状態が子どもへ与える影響などに興味を持つ。さらに、意識によってもたらされる変化を日々、体感を通して実践している。


