休み明け、何も変わらない気がしているあなたへ──教員人生を「整える」8つのシンプルな週間と仕込み
【更新日】
2025年8月13日(水)
コミュニケション・外国語運用能

また始まる。
けれど、何も変わらない
そんな気がしていませんか?
夏休みも半分が終わった頃。
「あれもやらなきゃ」「そろそろ準備しないと」
と思いつつ、
どこか憂うつな気分で過ごしている
教員の方も多いかもしれません。
去年の反省はある。
「今度こそ、もう少し余裕を持って」
と思っていた。
でも結局また、
忙しさの波にのまれてしまう気がしている。。。
そんなあなたにこそ、
「休み明けを迎える前にしてほしい
たった8つの習慣と仕込み」を、
そっと手渡したいと思います。
それは、子どもたちのためというよりも、
まずあなた自身が、
教員としての自分を保ち、
整えるための準備です。
⸻
1. 週1回「振り返りタイム」を手帳に書く
忙しい日々こそ、見過ごしてしまう「自分の気持ち」。
週に1回、15分でいい。
「今週はどんなことがあった?」
「今、何を感じてる?」
と問いかける時間を確保しておくと、
忙しさに飲まれた自分を
引き戻すスイッチになります。
それを学校が始まる前から準備してしておく。
少しでも習慣にしておく。
そんな些細なことで、私自身、救われた経験があります。
⸻
2. 「自分だけの『教育引き出しノート』」をつくる
学年が変わっても、担当教科が変わっても、
毎年変わらないもの。
それは「あなた自身の『感覚と工夫』」です。
おすすめなのが、自分の授業・関わり・気づき・アイデアを
1冊に集めた
「教育引き出しノート」をつくること。
デジタルでもアナログでもOKです。
たとえば、こんなふうに書いてみてはどうでしょうか。
•子どもがざわついたとき、うまくいった一言
•「静かに」「より伝わった」表現
•子どもが前のめりになった板書の工夫
•保護者懇談会で響いた声かけ
•自分の機嫌がよく保てた1日の流れ
こうした「経験のメモ」は、
学年が変わっても通用します。
そして、それはあなただけの
「教師の技術ストック」になります。
これをやるとどうなる?
• 異動や学年変更にビクビクしなくて済む
• すぐ授業に生かせる「引き出し」が増えていく
• 「自分って教員として何ができるんだろう?」という迷いが減る
• 自信や軸が、経験を通して育つ
こういったメリットがあります。
面倒だなと思うかもしれません。
でもスマホにパッと入れておいたり、
付箋で書いて項目ごとにまとめておいたりすると、
意外と便利で使えます。
⸻
3. 「職員室ストレス」の境界線を決めておく
誰かの機嫌に振り回される。
なんとなく居心地が悪い。
話したくないけど断れない。
そんな日常が、地味に心をすり減らします。
「昼休みは大人とは関わらず、子供とだけ過ごす」「毎朝10分だけ音楽を聴く」
「職員室は会議の時と、荷物を取りに行くだけ」
「また何か言われると嫌だな。今日は職員室に一瞬寄るだけで帰れるようにしておこう」
など、自分の守り方を最初に決めておくのは
大事な「セルフケア」です。
⸻
4. 「授業以外の感情労働」があることを認識する
教員の仕事は「授業」だけじゃありません。
保護者対応、同僚との人間関係、
子どもの感情のケア……。
もちろん、子ども、保護者、同僚によって
救われたり、喜びが増したり、感動したり。
それこそが教員の醍醐味です。
でも、反対にその全てが、
エネルギーを消耗させる感情労働になりうることも
頭の隅に入れておく。
それだけでも違います。
全て受け入れて、
全て受け止めていたら「疲れて当たり前」だと知っておくだけで、
自己否定が減ります。
⸻
5. 9月(夏休み明け)の「最優先タスク」を3つに絞る
やらなきゃいけないことは山ほどあります。
でも、すべてを完璧にこなそうとしないこと。
「まずこれだけはやる」と3つ決めておくことで、
エネルギーの分散を防げます。
人間ですから、出来ることに限界があります。
ついつい教員は何でもこなしてしまいがち。
それによって疲弊してしまいがち。
でもあえて、最優先を決めることで
そこに集中することができることに加え、
意外とそれ以外のことまでスムーズに進んでいくのです。
全てに同じエネルギーで関わるよりも、
力を入れるところ、抜くところを決めて取り組むことは
忙しい教員にとって必要なことです。
⸻
6. 「自己メンテ日」をあらかじめ手帳に予約
がんばるあなたに必要なのは、
「あとで休む」ではなく「休む前提」です。
1日休めないなら、半日でも。
半日が無理なら、夜だけでも。
「予定に入れておかないと、休めない」のが、
教員のリアルです。
手帳に入れた「メンテナンス日」は
罪悪感を持つことなく、
しっかり休んだり、好きなことをしたりしてください。
しっかり自分のメンテナンスをすることで、
あなたと関わる人たちに
良い影響を与えるのです。
⸻
7. 最初の3日間は「子どもとの関係づくり」に全集中
学級が安定するかどうかは、休み明け最初の3日間にかかっています。
指導よりルールより何より大事なのは、「先生は味方だ」と感じてもらうこと。
その関係性が、その後のすべての基盤になります。
⸻
8. 好きなもの・好きな時間に「触れてから」出勤する
学校が始まると、自分のことは後回しになりがち。
だからこそ、最初に「自分に栄養を与える時間」を取っておいてください。
お気に入りの音楽でも、コーヒーでも、小説でもいい。
あなたが機嫌よくいることが、
子どもたちへの最大のギフトです。
⸻
おわりに。
変わらない日々の中で、自分を変える
「今年も同じになりそう」と感じたときは、
「自分の整え方」をほんの少し変えてみてください。
全部やろうとしなくていい。
ひとつでも、できそうなものから取り入れてみてください。
教員としてのあなたが、あなた自身の人生の主人公であるために。
-------------------------
共育の杜のセミナー情報はこちらから
↓
セミナー情報
_________
この度、電子書籍を出版することになりました。
良かったら読んでみてください。
↓
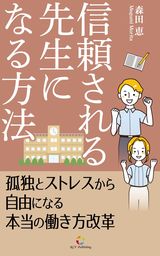
―――――――――
定期的に共育の杜からメルマガを配信しています。
↓
メルマガ登録はこちら
―――――――――
ブログに関しての質問や感想、聞きたいこと、トピックとして挙げてほしいことなどありましたら、下記までメッセージをください。
↓
こちらから
■ 執筆者情報■森田恵
子どもが好きで教員を目指すが、挫折。退職を考えるも奮闘し、次第に毎日が楽しく、子ども達からも「先生大好き!」と言われるように。そんな教員時代の経験をもとに、悩みを持つ人に役立つことを伝える活動を行っている。結婚を機に、渡米。10年の小学校教師の経験を活かし、渡米後は日本語の家庭教師や、現地校にて日本の文化を伝え、日本語を教えて過ごす。現在3児のママ。2度の流産経験により、食や環境、ママの状態が子どもへ与える影響などに興味を持つ。さらに、意識によってもたらされる変化を日々、体感を通して実践している。


