夏休み明け、子どもたちが「荒れる」のは当たり前?〜9月に教員がすべきたった一つのこと
【更新日】
2025年9月6日(土)
コミュニケション・外国語運用能
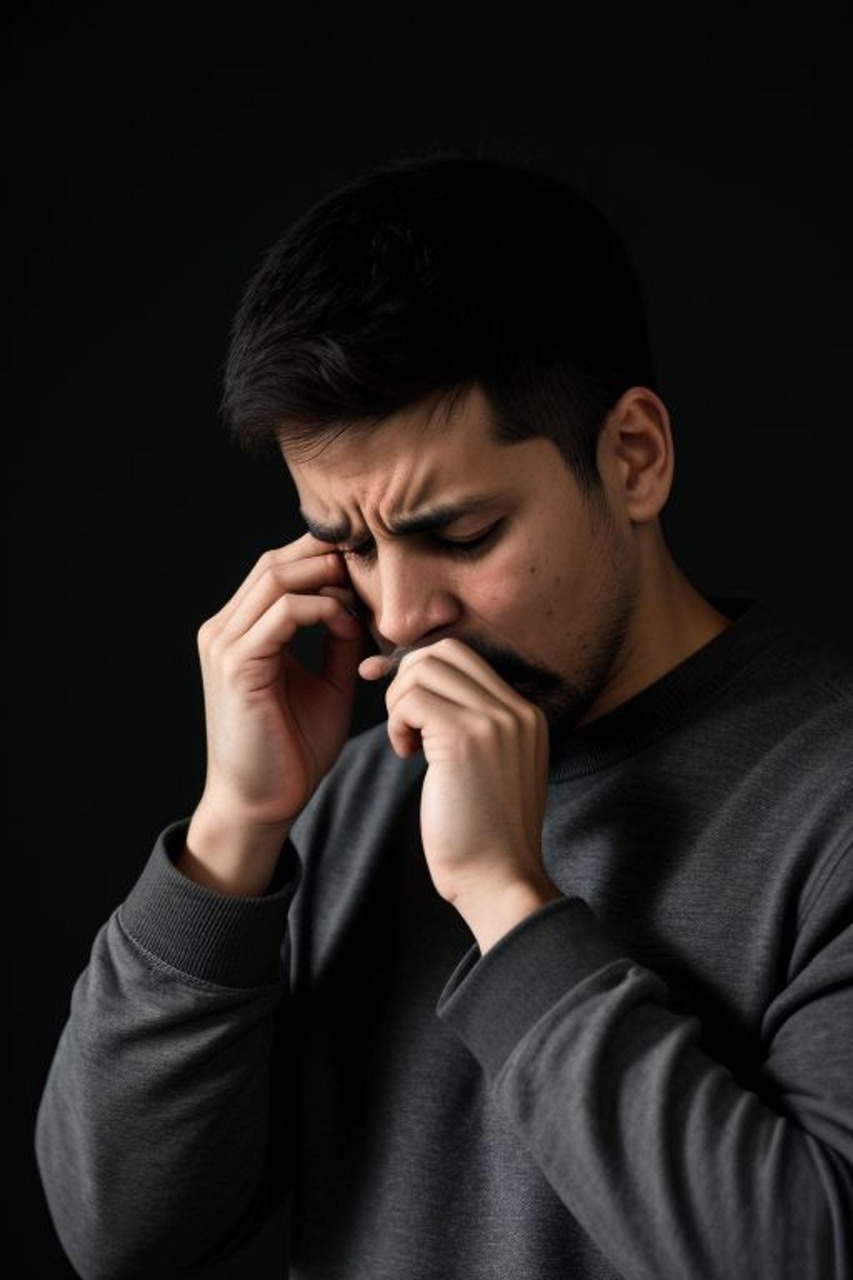
夏休み明け、クラスが落ち着かないのは「普通」です
9月、学校が再開すると、
「指示が通らない」
「子どもたちがザワザワしている」
「なんだか疲れる」
そんな声を毎年必ず聞きます。
でも、まず知ってほしいのは、
それはあなたの指導力不足ではなく、
「9月だから当たり前の現象」
だということです。
⸻
なぜ9月は揺らぐのか?
・長期休暇明けで生活リズムが乱れている
・学校のペースに戻るのに子ども自身も時間がかかる
・新学期初期に築いた「先生との距離感」がリセットされる
・安心してきたからこそ「試し行動」や「甘え」が出る
つまり9月の荒れは、
関係づくりが深まるサインでもあります。
教師も9月は揺らいでいる
子どもたちが夏休みからの切り替えに時間がかかるのと同じように、
教師自身も生活のリズムやエネルギーの配分が
変わります。
・長期休暇で「気持ちが緩む」
・授業や会議で急に忙しくなるギャップ
・学級経営を「また最初から」やり直す感覚
だからこそ、教員も「しんどい」と感じるのは自然なこと。
自分自身の揺らぎを認めることが、子どもに安心感を返していく第一歩になります。
教師がすべきたった一つのこと
それは、「もう一度、関係づくりに立ち返る」ことです。
叱って押さえ込むよりも、
まずは「安心感」を与える。
・「休み明けなのに、よく頑張ってるね」と声をかける
・授業をスモールステップで進めて「できた」を増やす
・個別に一言でも声をかける
こうした小さな積み重ねが、
揺らぎの9月を支える土台になります。
9月は「2度目の4月」
4月に子どもたちと築いたはずの
距離感やルールは、
夏休みを経てリセットされます。
だから「またゼロからやり直しか…」と
落ち込む必要はありません。
むしろ、4月よりも子どもたちを深く知った状態で、
関係づくりをやり直せるチャンス。
「もう一度自己紹介をしてみる」
「4月にやった活動をアレンジして再挑戦する」など、
小さな工夫で『2度目のスタート』を楽しく切れます。
すぐにできる実践アイデア
・朝の会で「9月の小さな目標」を子どもに発表してもらう・授業の最初に「リセット儀式」を取り入れる(深呼吸・一言感想・今日の宣言)
・荒れがちな子は、注意よりも「先に1つ褒める」
・教師自身も「今日はこれだけは伝える」と決めてシンプルにする
⭐️おすすめは「深呼吸」
呼吸は「自分の心を整えるリモコン」の
ようなものです。
不安やイライラで呼吸が浅くなると、
子どもも落ち着きません。
先生自身が深く息を吸い、
ゆっくり吐くだけで、
教室全体の空気が少し和らぎます。
・子どもと一緒に3回息を合わせる
・「吸う」よりも「吐く」を長めにする
これだけで、頭と心がリセットされ、
授業に入りやすくなります。
やってはいけないNG対応
つい次のような対応をしてしまいがちです。
・「休み明けなのにちゃんとできないの?」と子どもを責める
・授業を詰め込みすぎて子どもを疲弊させる
・学級の荒れを「自分のせい」と考え込む
これらは、子どもの不安をさらに大きくしてしまいます。
意識したいのは「少しずつ慣れていくのが当たり前」という視点。
教師自身も肩の力を抜きましょう。
おわりに
子どもたちが不安定なのは「失敗」ではなく「成長の揺らぎ」。
それにどう向き合うかで、今後の学級は大きく変わります。
焦らず、もう一度、
関係づくりから。
それだけで十分。
あなたの教室はまた整っていきます。
------------------------
共育の杜のセミナー情報はこちらから
↓
セミナー情報
_________
この度、電子書籍を出版することになりました。
良かったら読んでみてください。
↓
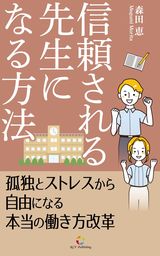
―――――――――
定期的に共育の杜からメルマガを配信しています。
↓
メルマガ登録はこちら
―――――――――
ブログに関しての質問や感想、聞きたいこと、トピックとして挙げてほしいことなどありましたら、下記までメッセージをください。
↓
こちらから
■ 執筆者情報■森田恵
子どもが好きで教員を目指すが、挫折。退職を考えるも奮闘し、次第に毎日が楽しく、子ども達からも「先生大好き!」と言われるように。そんな教員時代の経験をもとに、悩みを持つ人に役立つことを伝える活動を行っている。結婚を機に、渡米。10年の小学校教師の経験を活かし、渡米後は日本語の家庭教師や、現地校にて日本の文化を伝え、日本語を教えて過ごす。現在3児のママ。2度の流産経験により、食や環境、ママの状態が子どもへ与える影響などに興味を持つ。さらに、意識によってもたらされる変化を日々、体感を通して実践している。


