9月は「隠れ疲労」が溜まる季節。 心と体をいたわるヒント
【更新日】
2025年9月14日(日)
コミュニケション・外国語運用能

疲れてない?そんなあなたの心と体をいたわるヒント
夏休みが終わり、
新しい気持ちで迎える9月。
しかし、子どもたちの様子が
なんだか落ち着かなかったり、
自分自身の疲れがなかなか抜けなかったり、
と感じている先生は少なくないのではないでしょうか。
もし、次のようなことが心当たりがあるなら、
それはもしかしたら 「隠れ疲労」 のサインかもしれません。
・授業中に、なぜか声が出にくい
・子どもの小さなざわつきにもイライラしてしまう
・帰宅後、ソファに座ったまま動けなくなる
・朝起きても疲れが取れていない
夏休み中に蓄積した疲れと、
新学期の忙しさが重なる9月は、
心身のバランスを崩しやすい時期です。
自分でも気づかないうちに疲れが溜まり、
やがて心や体に不調として現れてしまう。
これが「隠れ疲労」の正体です。
教師のリカバリー習慣
心と体を回復させる6つのヒント
真面目で頑張り屋な先生だからこそ、
ついつい無理をしてしまいがちです。
しかし、あなたが元気でいられることが、
子どもたちにとって何よりの安心になります。
9月は、「頑張ること」よりも「回復すること」に意識を向けてみてください。
1. 「休むことに罪悪感を持たない」
放課後、職員室で
「まだやることが残ってるから帰れない」と
机に向かって頑張る先生の姿を
よく見かけます。
でも、その体はもう
悲鳴をあげていませんか?
やらなければならないことは
山積みかもしれませんが、
疲れ切った体と心では、
どんなに頑張っても
質の高い仕事はできません。
そんなときは、思い切って
帰る勇気を持つことも大切です。
「休むことも仕事のうち」だと、
自分に許可を出してください。
時には早く帰宅し、
自分の好きなことをしたり、
ただゆっくり過ごす時間を持ったりすることで、明日へのエネルギーを
チャージすることができます。
2. 「わずかな休憩を味方につける」
忙しい毎日の中で、
まとまった休憩時間を取るのは
難しいかもしれません。
しかし、たった1分、
いや数十秒でも、心と体を
リセットする時間は作れます。
・授業と授業の合間に、 深呼吸を3回 してみる。
・職員室の机で、 突っ伏して目を閉じる。
・教室から廊下に出て、 空を眺める。
・トイレに行って、 鏡の中の自分に「大丈夫」と声をかける。
または、ゆっくり一回でも深呼吸をする。
こうした「小さなリセット」を
こまめに挟むだけで、
その後の集中力や気持ちの持ちようが
まるで違ってきます。
3. 「話す場を持つ」
9月になると、
「クラスの子どもたちが落ち着かない」
「授業がなかなか進まない」
といった悩みを抱えやすくなります。
同僚と顔を見合わせ、「うちも…」と
ため息をつくことも多いのではないでしょうか。
そんなときに、「実は私も…」と
自分の状況を素直に話せるかどうかは、
とても重要です。
心の中にため込んでいると、
どんどん心が重くなっていきます。
誰かに話すことで、気持ちが楽になったり、
解決策が見つかったりすることも
少なくありません。
話す相手は、職場の同僚でも、
学生時代の友人でも、家族でも
構いません。
あるいは、声に出すのが難しければ、
ノートに自分の気持ちを
書き出してみるだけでも、
頭の中が整理されて
気持ちが落ち着く効果があります。
4. 「小さな達成感を味わう」
9月は、授業や行事の準備に追われて
「やることが終わらない」感覚に
押しつぶされがちです。
そんなときは、
あえて小さなゴールを
自分に設定してみてはどうでしょうか。
・今日の授業で「子どもに一度笑顔を返す」
・プリントを一枚でも整理できたらOK
・放課後10分だけ机を片付ける
こうした小さな達成を意識的に
積み重ねることで、
「今日も一歩進めた」という安心感が得られます。達成感は、心のガソリンです。
5. 「体をゆるめる習慣を取り入れる」
心の疲れと体の疲れはつながっています。
特に先生方は立ちっぱなし・
声を出しっぱなしで、
気づかないうちに全身に力が入っています。
授業後に肩をぐるぐる回す、
帰宅後にお風呂で深呼吸をする、
寝る前に布団の上でストレッチをする…。
わずか3分でも体をほぐすと、
心まで緩んでいきます。
「頑張る前に、まずは緩める」。
これを習慣にできると、
疲れがたまりにくくなります。
6. 「子どもたちと一緒にリセットする」
先生自身の回復は、
実は子どもたちとの関わり方にも直結します。
たとえば、授業の冒頭で子どもたちと一緒に
深呼吸をしたり、
窓の外の空を眺める時間をとってみたり。
ほんの数十秒でも、
クラス全体の空気が整うと同時に、
先生自身もリフレッシュできます。
「先生が元気でいることが、
子どもたちに安心を与える」と
先ほど書きましたが、逆もまた然り。
子どもと一緒に整う時間 を持つことで、
教室全体が落ち着きを
取り戻しやすくなります。
おわりに
教師という職業は、
子どもたちのために
頑張りすぎてしまう優しい先生が多いからこそ、
自分自身のケアがおろそかになりがちです。
9月は「整える」よりも
「ゆるめる」 を大切にしてみてください。
完璧を求めすぎず、
少し肩の力を抜いてみてください。
あなたが心身ともに健やかでいること。
それが、子どもたちにとって
何よりの教育であり、
安心感を与えます。
どうぞご自身を大切に、この9月を乗り切ってください。
------------------------
共育の杜のセミナー情報はこちらから
↓
セミナー情報
_________
この度、電子書籍を出版することになりました。
良かったら読んでみてください。
↓
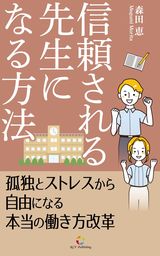
―――――――――
定期的に共育の杜からメルマガを配信しています。
↓
メルマガ登録はこちら
―――――――――
ブログに関しての質問や感想、聞きたいこと、トピックとして挙げてほしいことなどありましたら、下記までメッセージをください。
↓
こちらから
■ 執筆者情報■森田恵
子どもが好きで教員を目指すが、挫折。退職を考えるも奮闘し、次第に毎日が楽しく、子ども達からも「先生大好き!」と言われるように。そんな教員時代の経験をもとに、悩みを持つ人に役立つことを伝える活動を行っている。結婚を機に、渡米。10年の小学校教師の経験を活かし、渡米後は日本語の家庭教師や、現地校にて日本の文化を伝え、日本語を教えて過ごす。現在3児のママ。2度の流産経験により、食や環境、ママの状態が子どもへ与える影響などに興味を持つ。さらに、意識によってもたらされる変化を日々、体感を通して実践している。


